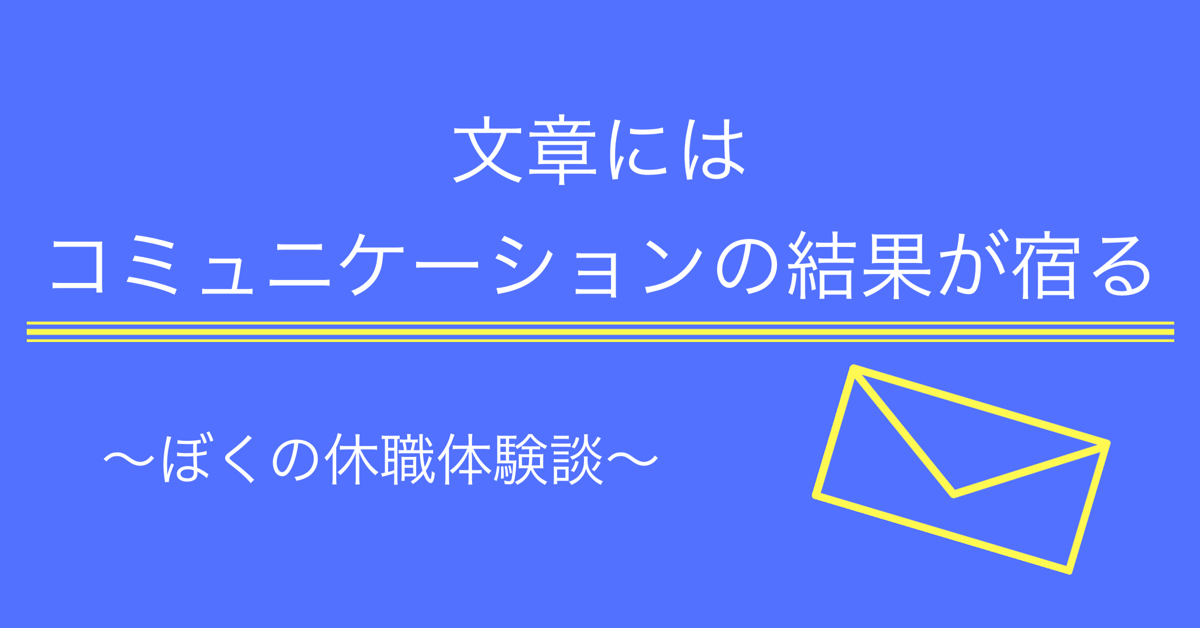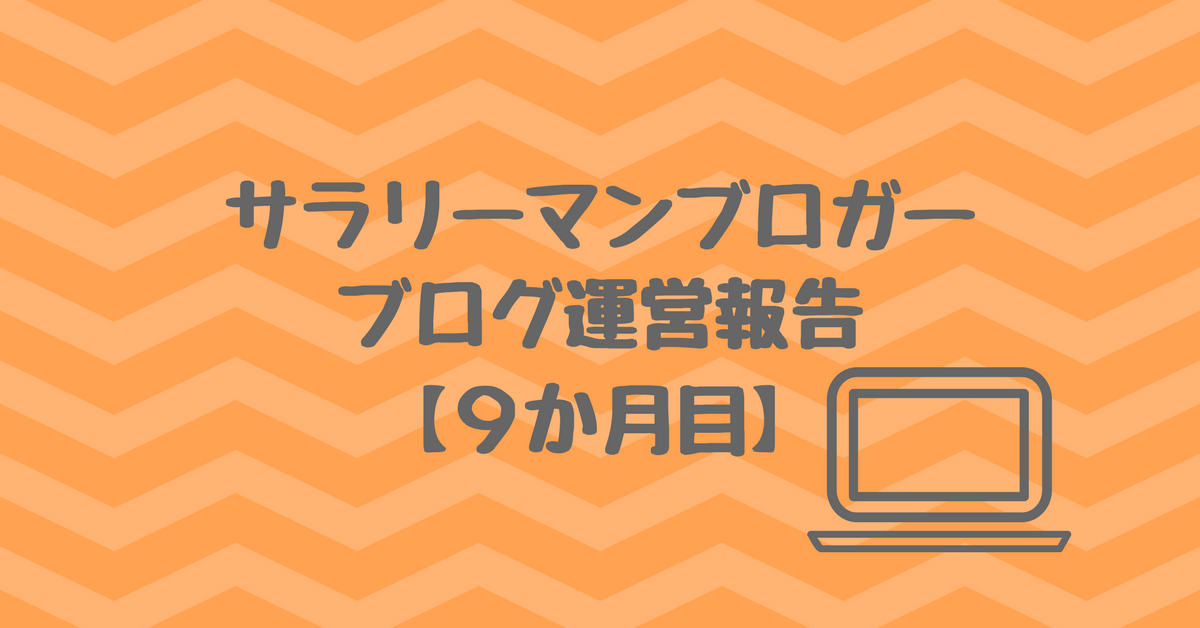この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
おはようございます。休職中のサラリーマンブロガー3まる(@3sunmaru)です。
普段から我々が目にしている“文章”。
人に何かを伝える際、“会話”と同様によく使われる手段ですね。
現在休職中なのですが、ぼくはこの“文章”が原因でメンタルが壊れ、体調を崩してしまいました。
休職して改めて何が辛かったか思い返すと、今までさほど気にしていなかった文章の持つ力に気付かされました。
その“文章の持つ力”とは、普段のコミュニケーションによって文章の捉え方は変わってくるということです。
書き方によって捉え方が変わるのはもちろんですが、同じ言葉を使ってもその文章を書いた人が普段どのように自分に接してくれているかで意味合いが変わります。
今回はこの“文章の持つ力”をぼくの休職体験談を例に出しながらご紹介します。
よくメールなど文章でやりとりする方や後輩・部下の上に立つ方はもちろん、働くすべての方に文章・コミュニケーションの大切さを改めて考えてみていただければと思います。
文章に潰された|ぼくの休職した原因
今回の気付きは“普段のコミュニケーションによっても文章の捉え方は変わってくるということ”。
まずは“普段のコミュニケーション”という前提部分からご紹介します。
高すぎる心理的コミュニケーションコスト
ぼくの所属するグループでは部署の毎日朝会後にミーティングの時間を設けています。
そのミーティングは仕事の進捗状況を共有したり、当日のタスクを確認したり、仕事で出てきた相談事などを話し合ったりする場でした。
ただ、実働隊の中では情報共有が済んでいたり、あらかじめ相談していたり、円滑なコミュニケーションが取れていたので、実質上司への確認の場と化していました。
しかし、ミーティングで上司に確認・相談すると怒鳴られる毎日。
指示が曖昧なため、最終的に提出する形を確認すると『そこまでいちいち指示を出さなければいけないのか…!』怒鳴られ、確認せずに自分たちの判断で資料を作成して提出すると『こういうのを求めていたんじゃない!』と怒鳴られ…
聞かないと怒鳴られるし、聞いても怒鳴られるし…
そんな上司とのコミュニケーションは心理的にハードルが高く、コミュニケーションコストが高すぎる状況にぼくもグループメンバーもうんざりしていました。
主なやりとりはメールの文章
席が別室である上に出張も多い上司。
そんな上司とのやりとりはメールが主でした。
対面でのやりとりについては、心を動かさないように努力した結果、ある程度聞き流すことができるようになりました。
上司との対面でのやりとりに疲れている方は、
一緒にオススメ!仕事のストレスが限界になる前に。ストレスから逃げる3つの“無動力”とは?
一緒にオススメ!理不尽な上司が教えてくれる仕事をする上で大切なこと
の2つの記事をご覧いただくと、何か心持ちが変わるかもしれません。
対面での言葉は聞き流せても、メールの文章は違いました。
2つ聞いても1つについて漠然と指示が返ってくるだけの返信。
読む側がどんな気持ちで読むかは考えていない言葉の選び方。
読むときに思い浮かぶのは怒鳴っている上司の顔と声。
心を疲弊させるその文章はメールという形で残り、何度も読み返すことができます。
全く読み返す必要のない上司からのメール。
ですが、書かれたことが心の中でこだまして、何度も何度も確認してしまいました。
そして、心はどんどん壊れていきました。
こうしてぼくは文章に潰されて休職を余儀なくさせられたのです。
同じ言葉でも普段のコミュニケーションで受け取り方が変わる
メール内には汚い言葉があった訳ではありません。(たまにはあったかも…)
いたって普通に使われる単語でも、普段から怒鳴り散らしている上司から送られてくる文章では威圧的に感じてしまいました。
例1:頼むよ!
例えば『頼むよ!』。
この“頼むよ!”からどんなイメージが浮かびますか?
もしも、普段から仲良くしていて、仕事を一緒にやっている先輩からきたメールに『頼むよ!』と書かれていたらどうでしょう?
ぼくは肩を叩きながらにこやかに『頼むよ!』と言っている姿をイメージしながら読んでしまいます。
『お願いね!』という風に言い換えられるでしょうか。
とりあえず、嫌な印象は受けないですね!
一方で、日常的に怒鳴っている上司から『頼むよ!』と書かれたメールが送られてきたらどうでしょう?
顔をしかめながら『頼むよ!』と言っている姿をイメージしてしまいます。
『頼むからしっかりしてくれよ…!』といった感じでしょうか。
威圧感・責められている感じがありますね…
例2:これ基本だから覚えてといて!
続いて『これ基本だから覚えといて!』という一文。
普段から仕事の相談をしたり、やり方を教えてもらったりしている上司からのメールだったら
[voice icon=”https://sunmaru.net/wp-content/uploads/2017/07/アイコン.png” name=”3まる” type=”l”]わかりました!覚えておきます![/voice]
という風に思えますが、普段から怒鳴っている上司からのメールだったらどうでしょう?
(こんなのもわかんねぇのかよ…!)というような思いが滲み出て見えませんか?
同じ一文なのに、一方では素直に受け入れられて、一方では責められているように受け入れられる。
なんとも不思議ですね…
例3:任せます
もう1つ。
『任せます』という単語です。
仲のいい上司・先輩からの『任せます』であれば、即決で
[voice icon=”https://sunmaru.net/wp-content/uploads/2017/07/アイコン.png” name=”3まる” type=”l”]そしたらこうしてみよう![/voice]
という風に判断してフットワーク軽く動き始めることができます。
普段から指示が曖昧で、察して決めると怒る上司・先輩からの『任せます』が来たらどうしますか?
ぼくだったら
[voice icon=”https://sunmaru.net/wp-content/uploads/2017/07/アイコン.png” name=”3まる” type=”l”]任せますって言われてもなぁ…
何しても怒られる気がする…
どうしようかなぁ…[/voice]
と無駄に悩んでしまいます。
普段から軽快なコミュニケーションがとれている場合は、コミュニケーションだけでなく行動も軽快にすることができます。
うまくコミュニケーションがとれないと、要件について考える時間が無駄に増えてしまいますね。
日常接する人への文章は普段からのコミュニケーションが重要
仕事を一緒にしたり、活動を共にしたりする人との文章のやりとりは、必ずその人をイメージしながら読むことになります。
すると、普段のコミュニケーションをどのようにとっているかで、読み手の受け取り方は変わってきます。
あなたが普段メールを送ったりしている相手とはどのようにコミュニケーションをとっていますか?
メールの文章は、相手があなたをイメージして読んで誤解を生まない表現ですか?
文章のやりとりは声・表情がわからないため、誤解が生まれやすいです。
相手がイメージする声や表情は普段のコミュニケーションから連想します。
文章には普段のコミュニケーションの結果が宿ると言っても過言ではありません。
文章の受け手に普段どのように接しているか。
文章を書くときにはこの視点も大切にしていきたいですね。
ブロガー視点で考えてみた
せっかくブログという文章を表現する場で文章について考えたので、このブログの書き手“ブロガー”という視点でも考えてみましょう。
ブログの読者はどういう方々でしょうか?
- 検索で来た方
- Twitterでフォローしてくださっている方
- Twitterでたまたま見かけて来てみた方
など、様々な方が想定できます。
では、どの方にフォーカスを当てて文章を書くべきでしょうか?
できる限り大勢の方に誤解なく内容を伝えたいものです。
そうなると検索で来た筆者のことを全く知らない方にフォーカスを当てて文章を書くべきでしょう。
全く筆者の人柄に触れていない人が読んで勘違い・誤解のない文章を書ければ、それは誰が読んでも勘違いのない文章になります。
(仲がいいが故に勘違いしてしまう可能性もなくはないですがね…!)
例えば、『会社員よりもフリーランスがいい理由5選!』というタイトルで記事を書くとしましょう。
検索から来た会社員の方が不快な思いをしないよう気をつけて文章を書きたいところです。
フリーランスがいいと言いつつも、会社員の方々に会社員を悪く言っているととらわれかねない表現は避けたいですね。
Twitterなどで普段から『会社員をディスっているわけじゃないですよ!』と言っていたとして、フォロワーさんなら読んで不快感を抱かなかったとしても、検索から来た筆者の人柄を知らない人がどう捉えるか。
ペルソナの設定も重要かもしれませんが、設定に依存しすぎて一般の読者の目線を忘れたような書き方にならないよう、気を付けて書いていきたいですね。
多くの方に読んでもらっているブロガーとして、今回の経験を自分の文章に活かしていければと思います。
まとめ:読む相手がどう受け取るかを考えて文章を書きたい!
この記事では休職に至る体験から、文章には普段のコミュニケーションの結果が宿るということについてお伝えしました。
▼ 文章には普段のコミュニケーションの結果が宿るという気付き ▼
◯ 休職に至った普段のコミュニケーションとは?
- 心理的なコミュニケーションコストが高すぎた
- 上司とのやりとりはメールが主だった
◯ 同じ言葉でも普段のコミュニケーションで受け取り方が変わる
○ 日常接する人への文章は普段からのコミュニケーションが重要
- 文章を読むときは書き手をイメージしながら読む
- 文章の受け手と普段どのように接しているかという視点が大切
◯ ブロガー視点で考えてみた
- Twitterからの流入もあるだろうが、検索から来る人の立場に立って書きたい
同じ言葉でも受け取る人によってイメージが変わる文章は、奥が深く、難しさ・面白さがあります。
受け手が見えている文章は、その人と普段どのようにコミュニケーションをとっているか、自分はその人にとってどんな存在なのか、相手の立場に立って書いた方が誤解のない文章になります。
受け手が複数いる文章は、自分の人柄を最も知らない人に対して書いている視点を忘れずに、どうやったら自分の伝えたいことが正しく伝わるかということを考えながら書いた方がいいですね。
メールでのやりとりが多い方、後輩・部下の上に立って仕事をしている方、そして働くすべての方々。
自分の文章に勘違いが生まれそうな部分はないか、無意識のうちに威圧的・攻撃的になっている部分はないか、ぜひ読み手の立場で考えてみてください。
文章の確認も大事ですが、普段のコミュニケーションのあり方も重要な文章の要素です。
改めて周りとの接し方を振り返ってみてもいいかもしれませんね!
Twitterをフォローしていただけると嬉しいです。