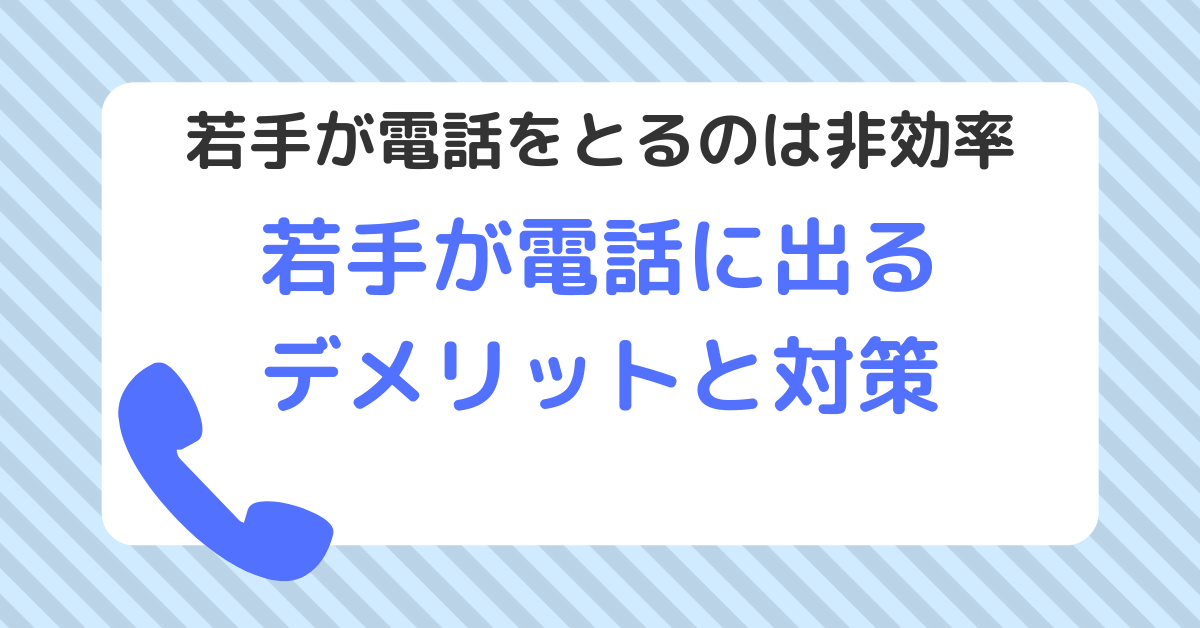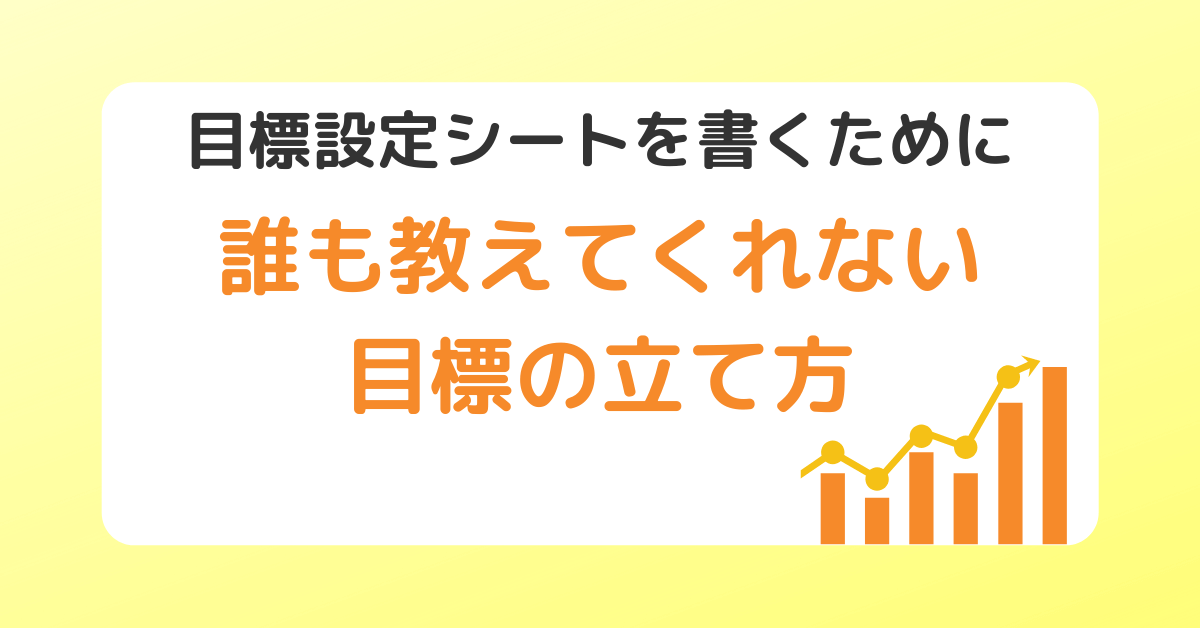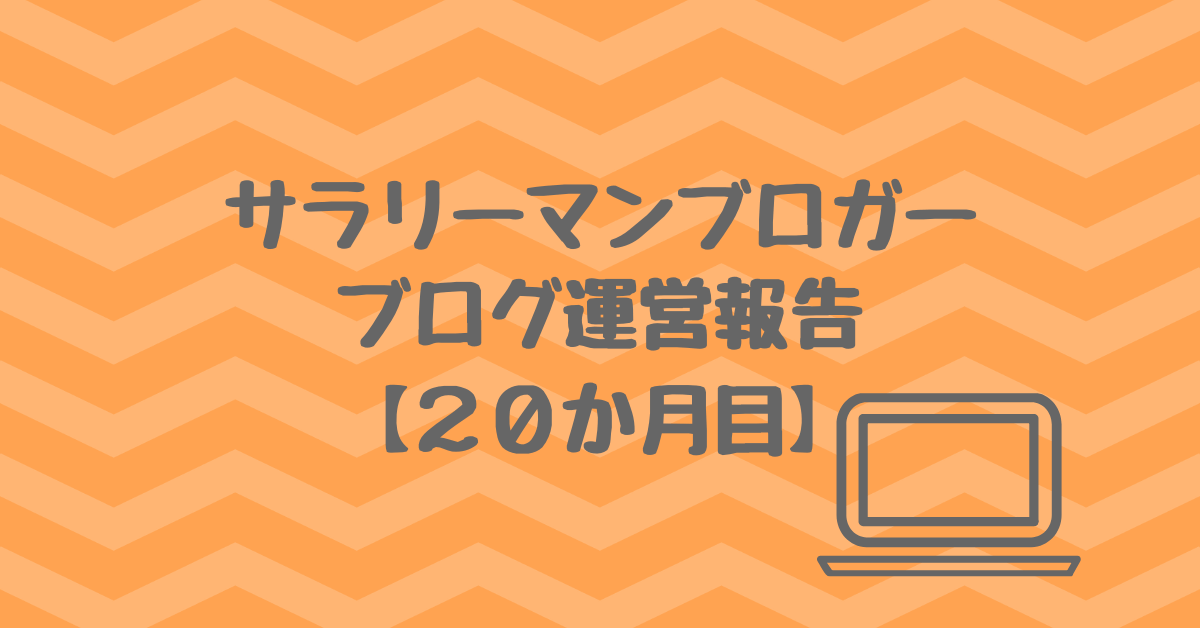この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
先日仕事で怒られたところ、スズメが訴えかけてきました。
若手が電話取るってルール古いと思うんですよ。
それは人が余ってて若手の仕事が少なかった時代の話じゃないですか?
今は若くてもたくさん仕事があります。電話番している余裕は正直ないです。
電話取れというなら、代わりにこっちの仕事やれと言いたいってスズメがこっちを見つめて訴えてきます。— 3まる@駆け出しブロガー (@3sunmaru) 2017年9月20日
普段Twitter上ではほとんど反応がもらえないのですが、このツイートは思いの外反響がありました。
やはり今の若い世代の方々は電話をとるルールに疑問を感じているようです。
ということで、この記事では若手が電話をとるルールのデメリットと対策、そして本来あるべき姿についてお伝えします。
もし電話をとることで仕事が中断されて困っているようでしたら若手に限らずお読みいただけると幸いです。
若手が電話に出ることによる仕事中断のデメリット
慣れない若手の仕事がむりやり中断される
電話とは基本的に外部の方が内部の事情を知らずにかけてくるものです。
となると、当然そのタイミングの良し悪しは運次第。
自分が仕事中であっても“若手が出る”というルールがある場合、仕事を中断して電話に出ざるを得ません。
もちろん、仕事は強制的に中断されます。
電話は唐突にやってくるのできりのいいところまで仕事を進めてから…なんてことはできません。
中途半端でも電話に出なくてはならず、結果としてどこまでやったかわからなくなったことが多々あります。
さらに職場によっては電話に出るまでのスピードを要求される場合もあると思います。
そうなってくるとなにをしていたか、どこまでやっていたか覚えておくのは非常に困難です。
若いうちだとなおさらではないでしょうか?
手探りで仕事を進めているのに、さらに電話で仕事を強制中断させられる。
これでは仕事効率も大幅に落ちます。
ミスも多くなります。
若手が仕事を中断して電話をとるというのはかなりの負担です。
若手に仕事の電話がかかってくることは滅多にない
これは自分の職場だけの話かもしれませんが、若手は少し年上の先輩と組んで仕事を進めます。
すると、電話がかかってきても自分宛なんてことは滅多にありません。
つまり電話をとったとしても必ず誰かに回す必要があります。
これ、電話をとる意味ありますか?
余計な仕事が増えていますよね?
相手も待たせて迷惑をかけていませんか?
自分宛でない可能性が高いのに電話に出るくらいなら、最初から電話がかかってくる可能性が高い人が出た方がよっぽど効率的だと思います。
さらに、ぼくの職場ではひどいことに、先輩方は自席にいることは少ないです。
どこにいるかわからない。
いつ戻ってくるかわからない。
挙句の果てに今日帰ってくるかわからない場合すらあります。
散々相手を待たせた挙句、見つかりませんでしたなんてことも多々…
本当に時間と労力の無駄です。
ぼくは効率重視なので現在の職場に来てから、より一層電話に出たくなくなりました。
若手ができる電話による仕事の中断の対策
ルールとして若手が電話に出るとある以上、従う以外ありません…
ですが、対策もないわけではありません。
それは若手で協力して時間ごとに割り振るのです。
- 10時〜11時:山田
- 11時〜12時:田中
- 13時〜14時:佐藤
- 14時〜15時:山田
- …
という風にです。
不服かもしれませんが、電話番の時間は中断しても影響の少ない仕事をします。
すると若手が電話をとるというルールを守りつつ、仕事の中断を最小限にすますことができます。
協力してくれる先輩・後輩がいる職場ではぜひお試しください。
電話による仕事の中断解決に向けた本質的な話
固定電話は誰が出るかわからない、ある種テロのようなものです。
電話テロ。
では、よくかかってくる固定電話への電話。
これは必要だからかかって来ているのでしょうか?
携帯ではダメなの?
電話をかける方も誰が出るかわからないよりは、相手が出るか出ないかの2択、そして出なかった場合はメッセージを残せる携帯電話を使った方がよっぽど効率的ではないでしょうか?
今の時代、携帯電話を持っていないなどということはないでしょう。
また、今ではWebも発達してインターネットを用いた通話手法も数多く確立されています。
電話代がかかり過ぎるとかは言い訳に過ぎないと思っています。
企業は業務用携帯の支給もしくはSkypeなどの通信手段の有効活用に積極的に取り組むべきです。
誰も出なくてもいいんじゃない?
電話は必ずとらなければならないのでしょうか?
みんな手が放せなかったり、作業に集中しているのであれば出なくてもよいのではないでしょうか?
かけてきた人だって、必要とあれば電話がつながらなかった時点で別な方法を考えるはずです。
先に述べた携帯という選択肢もありますし、メールという方法もあります。
スマホが普及した今、連絡ツールはいくつもあるのであらかじめ連絡をつけやすい方法で連絡先を交換するということも考えられます。
目的の人と違う人が出る可能性のある電話。これに変わる手段をそろそろ確立しませんか?
まとめ:若手が電話をとるのはどう考えても非効率。電話による仕事の中断の影響はより大きいと心得よ。
やはりどう考えても自分の仕事を中断したり、集中を切ったりして対応するべきものとは思えません。
そもそも、この若手が電話をとるルール、“バブル世代の負の遺産”と考えています。
人が余っていて、若手は仕事が少ないから電話に出ておいてほしい。
そんな要望に答えた結果、“若手は電話に出ておいてほしい”だけが残ってしまった。
これが脈々と受け継がれ暗黙のルールとなってしまったというのが実情では?
今や若手も仕事まみれ。
電話に出るから仕事をやってくれ状態です。
暗黙のルールは明文化されていない分、普段意識しないところに溶け込んでいてなかなか見直されません。
これを改善するためには、現在電話に出さされて嫌な思いをしている我々若い世代が、数年後・十数年後に同じことを繰り返さないことが必要なのかもしれません。
以上、サラリーマンブロガー3まる(@3sunmaru)でした!